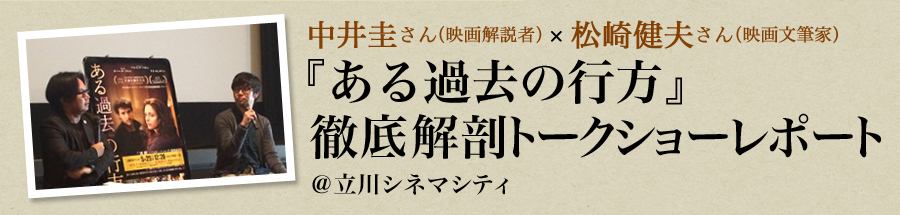
公開6週目となった5月某日、前日より公開となった立川シネマシティで、映画をこよなく愛する中井圭さんと松崎健夫さんのお二人をゲストに迎え、本作を徹底解剖するトークショーを開催しました!その全貌をレポートいたします。
途中ネタバレも含みますのでご注意を。(以下敬称略)
 この監督の『別離』とか『彼女が消えた浜辺』とかの過去作もそうなんですけど、話だけ追っていくと、たんなる人間ドラマというか人間の確執を描いているっていうことですよね。でも、それだけだと人によっては共感する人がいないとか、いろんな人物がいすぎて誰に感情移入すればいいのかわからないってことがでてきてしまう。でも実は、その誰に感情移入したらいいのかわかんないってこともじつはこの人の狙いじゃないかと僕は思ってて。例えば、世間一般の世の中みたときに、いろんな人いるじゃないですか。いろんな考え方の人がいるから、この映画って、普通の、例えば単純なハリウッド映画なんかの脚本の作り方からいくと良い人と悪い人とか、敵対する人と主人公になる人がいて、その対立構造とかそこから生まれるものを乗り越えていくっていう物語にするんだけど、ファルハディ監督の場合は、いろんな考えの人をわざと存在させているんですよね。だから人によっては、あ、この人は共感できないけど、この人の言うことはわかるとか、この登場人物のなかだったらこの人に考え方近いんじゃないかなってなると思うんだけど、それは世の中がそうだからってことで。それを毎回描いている監督だなと思いました。
この監督の『別離』とか『彼女が消えた浜辺』とかの過去作もそうなんですけど、話だけ追っていくと、たんなる人間ドラマというか人間の確執を描いているっていうことですよね。でも、それだけだと人によっては共感する人がいないとか、いろんな人物がいすぎて誰に感情移入すればいいのかわからないってことがでてきてしまう。でも実は、その誰に感情移入したらいいのかわかんないってこともじつはこの人の狙いじゃないかと僕は思ってて。例えば、世間一般の世の中みたときに、いろんな人いるじゃないですか。いろんな考え方の人がいるから、この映画って、普通の、例えば単純なハリウッド映画なんかの脚本の作り方からいくと良い人と悪い人とか、敵対する人と主人公になる人がいて、その対立構造とかそこから生まれるものを乗り越えていくっていう物語にするんだけど、ファルハディ監督の場合は、いろんな考えの人をわざと存在させているんですよね。だから人によっては、あ、この人は共感できないけど、この人の言うことはわかるとか、この登場人物のなかだったらこの人に考え方近いんじゃないかなってなると思うんだけど、それは世の中がそうだからってことで。それを毎回描いている監督だなと思いました。
 最近映画評論でも言われる、直接的に描くって言うのがどうかっていう議論は今回おいとくにして、例えば我々が実生活を生きていて、誰彼が亡くなりましたと訃報を受けてお葬式に行くときは、おそらく死んだ瞬間を見てる人っていうのは、ごく一部の人以外ほとんどいないわけですよ。でもすごく親しい人だったら、その人の過去のこととか思い出して、葬式のとき涙があふれるってことがあると思う。この監督がやっているのは同じことで、その場にいなくてもそれまで積み上げてきた演出によって画面を観ていると、この映画だったら彼らが家族に対してどういう感情を持っていたのかってことを思い図る、考えられるようになってる。映画の手法で一番わかりやすいのはフラッシュバックって言って回想シーンてあるじゃないですか。過去に戻って昔の事を思い出すっていくらでもあると思うんですけど、この監督って一切しないんですよ。
最近映画評論でも言われる、直接的に描くって言うのがどうかっていう議論は今回おいとくにして、例えば我々が実生活を生きていて、誰彼が亡くなりましたと訃報を受けてお葬式に行くときは、おそらく死んだ瞬間を見てる人っていうのは、ごく一部の人以外ほとんどいないわけですよ。でもすごく親しい人だったら、その人の過去のこととか思い出して、葬式のとき涙があふれるってことがあると思う。この監督がやっているのは同じことで、その場にいなくてもそれまで積み上げてきた演出によって画面を観ていると、この映画だったら彼らが家族に対してどういう感情を持っていたのかってことを思い図る、考えられるようになってる。映画の手法で一番わかりやすいのはフラッシュバックって言って回想シーンてあるじゃないですか。過去に戻って昔の事を思い出すっていくらでもあると思うんですけど、この監督って一切しないんですよ。
 声が届かないシーンをこの後も重ねてますし、それと、関係性にしても、この映画の主要な登場人物3人いるじゃないですか。映画を観た印象で言うと、イランから来た人(マリー=アンヌの元夫、アーマド)がね、一番まともやな、みたいな感じさせると思うんですけど。でも実は3人とも不完全ですよっていうのを画面の中で示唆しているんですね。それはどういう風にかっていうと、例えば冒頭で(アーマドを)迎えに行ったマリー=アンヌが、駐車場からバックで出ていくシーンがあるじゃないですか。何か飛び出してきて、急ブレーキを踏むっていう。あれがまずひとつ。その後、アーマドの運転する車でふたりで家に向かう途中、道を間違えるんですね。そして今度は、サミール(マリー=アンヌの現在の恋人)と一緒に道路を歩いてるときに、マリー=アンヌが横断歩道を渡ろうとして危ないってなる。つまり全部、登場人物のミスですよね。人間のミスっていうものがそのとき一緒にいる人との関係性ってものを示唆する構造になってる。もしふたりでいる時に道を渡れる、うまく発進できていることであれば、関係性がきちんと成立しているってことなんだけど。ここでは逆にふたりでいる時に何かが起きてしまう、つまり、うまくいかないってことを示唆している。映画を観ていると何となく違和感を感じるんですけど、このアスガー・ファルハディって天才なので。ちょっとなんか違和感があるかなっていう画には全て何かしらの意味が入っていると思ってて間違いないと思うんですね。
声が届かないシーンをこの後も重ねてますし、それと、関係性にしても、この映画の主要な登場人物3人いるじゃないですか。映画を観た印象で言うと、イランから来た人(マリー=アンヌの元夫、アーマド)がね、一番まともやな、みたいな感じさせると思うんですけど。でも実は3人とも不完全ですよっていうのを画面の中で示唆しているんですね。それはどういう風にかっていうと、例えば冒頭で(アーマドを)迎えに行ったマリー=アンヌが、駐車場からバックで出ていくシーンがあるじゃないですか。何か飛び出してきて、急ブレーキを踏むっていう。あれがまずひとつ。その後、アーマドの運転する車でふたりで家に向かう途中、道を間違えるんですね。そして今度は、サミール(マリー=アンヌの現在の恋人)と一緒に道路を歩いてるときに、マリー=アンヌが横断歩道を渡ろうとして危ないってなる。つまり全部、登場人物のミスですよね。人間のミスっていうものがそのとき一緒にいる人との関係性ってものを示唆する構造になってる。もしふたりでいる時に道を渡れる、うまく発進できていることであれば、関係性がきちんと成立しているってことなんだけど。ここでは逆にふたりでいる時に何かが起きてしまう、つまり、うまくいかないってことを示唆している。映画を観ていると何となく違和感を感じるんですけど、このアスガー・ファルハディって天才なので。ちょっとなんか違和感があるかなっていう画には全て何かしらの意味が入っていると思ってて間違いないと思うんですね。 実はその子どもが持っている眼差し自体が、本質に一番近いものというふうにとらえると、大人が見たとき、ほんとに子どものわがままにしか見えないんだけど、もう少し俯瞰してみると、一番冷静に物事見てるんじゃないかっていう。それはほんとにさっき言ったように『別離』もそうだったしさっきの『フライト・パニック』とかもそうなんだけど、子どもの存在をそういうふうに描いているっていうことなんですよね。それにはイランていう国が起因しているのではと思う。イランでは、ほとんどの映画って政府の支援がないと、作れるんだけど、国内で上映できないわけですよ。この監督もイランから追い出された監督のことを擁護したりして政府からにらまれたりもしていて。イランで最も有名なアッバス・キアロスタミ監督もインタビューで言っていたんですが、イラン映画に子どもを主人公にした映画が多いのは、世の中の訴えたいことを子どもの立場に置き換えて描くことでしかできないからだと。だからこそ、そこにこそ本当に描きたいことがあるってことが、イランの監督の中にあるんじゃないのかなと思いますけどね。
実はその子どもが持っている眼差し自体が、本質に一番近いものというふうにとらえると、大人が見たとき、ほんとに子どものわがままにしか見えないんだけど、もう少し俯瞰してみると、一番冷静に物事見てるんじゃないかっていう。それはほんとにさっき言ったように『別離』もそうだったしさっきの『フライト・パニック』とかもそうなんだけど、子どもの存在をそういうふうに描いているっていうことなんですよね。それにはイランていう国が起因しているのではと思う。イランでは、ほとんどの映画って政府の支援がないと、作れるんだけど、国内で上映できないわけですよ。この監督もイランから追い出された監督のことを擁護したりして政府からにらまれたりもしていて。イランで最も有名なアッバス・キアロスタミ監督もインタビューで言っていたんですが、イラン映画に子どもを主人公にした映画が多いのは、世の中の訴えたいことを子どもの立場に置き換えて描くことでしかできないからだと。だからこそ、そこにこそ本当に描きたいことがあるってことが、イランの監督の中にあるんじゃないのかなと思いますけどね。 ラスト、ラジコンが飛ばないじゃないですか。あれは、行く末を表してるんじゃないかなって言う。何を語らずともあそこも不穏な感じがあるじゃないですか。飛んで行ったらこう、上を見上げて、なんか希望的な感じがあるけれども、飛ばないんですよね。そういうとこも、人によって解釈はいろいろあっていいと思うんだけれども、明らかにこうですよってことを監督は避けたいのかなと。というのはさっきも言ったように、世の中にはいろんな人がいて、いろんな考えた方があるので、こうですよって言ってしまったときには、なにかあったときに解決方法が一つしかないってことになっちゃう。そうじゃなくてそれぞれの解決の仕方があるんじゃないかっていうところで、監督としてはヒントというか自分の意思表示としてはラジコンが飛ばないということで示してはいるけれども、観ている方々にいろいろと考えていただきたいと言ってるんじゃないかなと僕は思う。
ラスト、ラジコンが飛ばないじゃないですか。あれは、行く末を表してるんじゃないかなって言う。何を語らずともあそこも不穏な感じがあるじゃないですか。飛んで行ったらこう、上を見上げて、なんか希望的な感じがあるけれども、飛ばないんですよね。そういうとこも、人によって解釈はいろいろあっていいと思うんだけれども、明らかにこうですよってことを監督は避けたいのかなと。というのはさっきも言ったように、世の中にはいろんな人がいて、いろんな考えた方があるので、こうですよって言ってしまったときには、なにかあったときに解決方法が一つしかないってことになっちゃう。そうじゃなくてそれぞれの解決の仕方があるんじゃないかっていうところで、監督としてはヒントというか自分の意思表示としてはラジコンが飛ばないということで示してはいるけれども、観ている方々にいろいろと考えていただきたいと言ってるんじゃないかなと僕は思う。